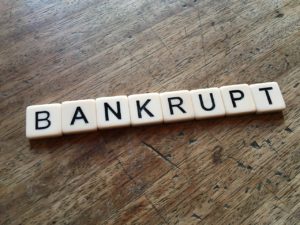不動産投資は、家賃収入から経費を差し引いたキャッシュフローが重要とよく言われますが、キャッシュフローはあくまでも利益確定までの収益であり、売却によって利益確定をしなければ最終的な損益は確定しません。最終的な利益を決めるのは、売却時の不動産の価値と税金です。
本記事では、不動産投資の収益構造と利益を決める要素について解説します。
目次
不動産投資の収益構造
不動産投資の収益構造は、以下のとおりです。
不動産投資の収益=①保有期間中のキャッシュフロー累計+②売却益(損)
①キャッシュフローとは、家賃収入から経費を引いた、毎月の現金収入のことです。キャッシュフローは、不動産投資の収益の源泉となります。
キャッシュフロー累計=賃料収入-(ローン元金返済-支払金利-経費-税金)
②売却益とは、不動産を売却したときに得られる利益のことです。売却益は、不動産の価格から取得価格を引いた差額です。
売却益=売却価格-(頭金-ローン残債-経費-税金)
対象の不動産を売却をしないと最終的な損益は確定しないのが不動産投資です。
株も同じですが、保有期間中の損益は含み益(含み損)です。
「いつか現金化する」という視点を持たずに不動産投資をすると、最終的に損をしたり、売却時の税金支払いの用意が足りないなどの可能性があるので、所有不動産の価値は常に気にかけておく必要があります。
多くのキャッシュフローの累積が貯まっていても、売却をしたときに多額の売却損が出てしまえば結果として投資そのものはそれほど儲からなかったということになる可能性は十分にありえます。
物件選定の時点から現金化しやすく、価格変動リスクの低い地域の物件を選ぶことが大切です。
利益を決める要素
不動産投資はキャッシュフローが重要とよく言われます。
これは正しいのですが、キャッシュフローだけで判断するのは間違いです。
不動産投資は建物を貸して、その対価として家賃をもらうものです。
建物が古くなれば家賃は下落して最終的に建物には価値がなくなります。
最終的に不動産投資は、日々の運営で得られるキャッシュフローと収益を生む建物の建っていた土地が資産ということになります。
一般的にキャッシュフローの多くなる物件は地方都市の高利回り物件ですが、地方都市の物件は土地の価値が低く、建物の劣化で売却する時に購入価格を大幅に下回る可能性があります。
さらに多額の減価償却を経費として先に計上しているので、売却価格が購入価格を大幅に下回っても売却益がでてしまい譲渡所得税を払う可能性もあります。
キャッシュフローだけに注目しすぎると最終的に投資に失敗している可能性もあるので気を付けましょう。
参考:収益物件売却時の税金
個人の場合、キャッシュフローは累進の所得税率、売却益は保有期間による譲渡所得税率で税額が計算されますので、税率を比較してどちらを重視すると得か考えても良いと思います。
保有期間中の利益はあくまで含み益であり、売却をしなければ損益は確定しないということです。
キャッシュフローだけでなく売却までの収支を税引き後で考えておく必要があります。
家賃の売却価格への影響
投資用不動産は「家賃収入÷利回り」で価格を算出します。
家賃が下がると売却金額も下がるということになります。
築年数の経過によって家賃が下がるのは仕方のないことですが、築年数相応の減価なのか周辺物件と比較しておくことが大切です。
必要以上に家賃を下げるということは売却時に得られる利益を失っていることと同じことになるからです。
家賃を適正に保つことが最終的な利益のために必要です。
不動産投資で払う税金
不動産投資は税金との闘いとも言えるほど、税金は収支に大きな影響があります。
シミュレーションを行う時には必ず税引き後の数字を確認しましょう。
不動産投資で個人が支払う税金
- 所得税(所得の5%~45%で累進)
- 復興所得税(所得税額の2.1%)
- 住民税(所得の約10%+均等割)
- 個人事業税(不動産所得の290万円超の部分に5%)
- 売却時の譲渡所得税(保有期間5年以下:39.63%、5年超:20.315%)
- 固都税
不動産投資で法人が支払う税金
- 法人税(全ての事業合算で税引前利益800万円までの利益に25%、800万円超の部分に37%)
- 法人住民税(法人税額の12.9%+均等割7万円)
- 法人事業税(税引前利益の5%)
- 地方法人特別税(法人事業税の43.2%)
- 地方法人税(法人税額の4.4%)
- 固都税
参考:不動産投資の必要経費と税務上の取扱い 物件取得時
不動産投資の必要経費と税務上の取扱い 物件保有期間
自分が投資をした時にはどの税が税率何%でいくら支払うのか事前にチェックしましよう。
不動産投資の利益 まとめ
不動産投資で成功するためには、キャッシュフローだけでなく、売却益もしっかりとシミュレーションしておくことが大切です。
不動産投資は、数字とロジックです。
現金化したときの不動産の価値と税引き後の収支シミュレーションを行ない、資産価値の高い不動産に投資を行うことで、失敗を防ぐことができます。
家やお金の悩み、お気軽にご相談下さい初回相談無料受付時間 9:00-18:00
[ 土・日・祝日除く ]